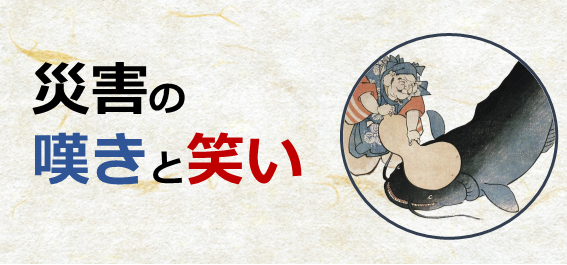第1章 災害列島・日本 ― 歴史に見る災いの痕跡
6. 『日本書紀』 30巻15冊
慶長15(1610)年刊
【所蔵情報】
日本最初の国史。天武天皇期(670年代)編纂開始と推測され、舎人親王(676-735)らの撰で養老4(720)年完成。巻29に天武13年10月14日(684年11月26日)の地震記事を載せる。「山崩れ河涌き、諸国郡の官舎及び百姓の倉屋、寺塔神社、破壊の類あげて数うべからず」とあり、伊予の温泉が出なくなり、土佐国の田地が海中に没したと記し、「未曽有也」という古老の言を付す。推定マグニチュード8.0の南海トラフ地震と考えられている。なお5月には彗星の記事を載せるが、これはハレー彗星に関する日本最古の記録である。
7. 『日本三代実録』 50巻20冊
源能有ほか撰 [京都] : 野田庄右衞門 寛文13(1673)年跋
【所蔵情報】
『日本書紀』から続く国史「六国史」の最後で、天安2(858)-仁和3(887)年を対象として延喜元(901)年成立。本書は地震の記事が多い。貞観10年7月(868年8月) の地震では8日に京都内外の家屋や垣根が崩壊した。その後も連日地震が起き、15日に播磨国(現兵庫県南西部) から「諸郡の官舎、諸定額の寺堂塔、皆尽くくずれ倒れる」と報告された。また貞観11年5月(869年7月) には「陸奥国大地震動」し、昼のような光が点滅したと書く。平成23(2011)年東北地方太平洋沖地震に先立つと言われた陸奥国大地震・津波の記事である。
8. 『方丈記』 1冊
[京都] : 村上根来寺 正保4(1647)年刊
【所蔵情報】
デジタルコレクション
平安末~鎌倉初期の随筆。京都で隠遁生活を営んだ鴨長明(1155-1216)の作で建暦2(1212)年成立。中では京都で起きた安元3(1177)年の安元大火、治承4(1180)年の辻風(突風)と平家の福原遷都、養和年間(1181-82)の飢饉、元暦2(1185)年の京都地震(文治地震)とそれらへの感想を綴っている。京都地震は琵琶湖西南岸が震源と推定され、主に京都東部で大きな被害を出した。長明は「おそれの中に恐るべかりけるハ只地震也」と書き、また「其余波しばしば絶ず、よのつねに驚くほどの地震二三十度ふらぬ日はなし」と頻繁に続いた余震へ言及している。
9. 『折たく柴の記』 3巻3冊
新井白石著
【所蔵情報】
デジタルコレクション
儒学者である新井白石(1657-1725)の自叙伝。享保元(1716)年起筆。内容は徳川第6代将軍家宣の下で幕政に関与した事蹟が中心だが、自らの生い立ちなどを述べる上巻の末尾近くで元禄16年11月23日(1703年12月31日)江戸地震(元禄地震)と宝永4年11月23日(1707年12月16日)富士山噴火に伴う降灰の体験記を載せる。地震の際、白石は夜中の震動で怯える妻子を家に留め、裃に着替えて主君の甲府徳川家へ出仕した。降灰の際、白石は正午頃に西の空にかかる黒雲と雷鳴を見ており、地鳴りや地震も続いたと記す。白石が富士山噴火の情報を得たのは25日頃だった。