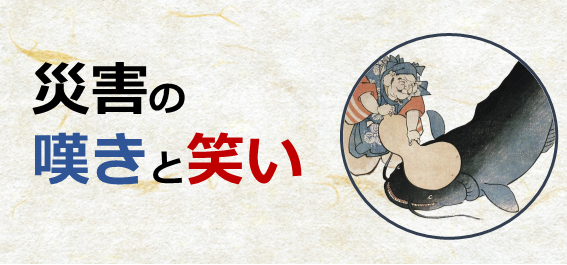
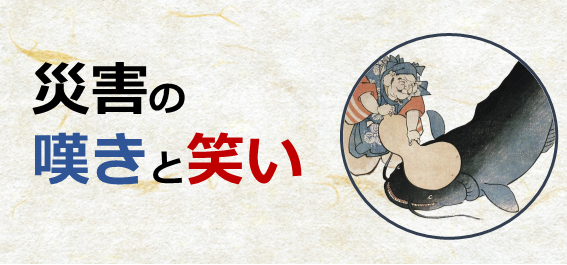
本日は、令和7年度筑波大学附属図書館特別展「災害の嘆きと笑い ―日本人の記憶とこころ―」にお越しいただき、誠にありがとうございます。主催者を代表し、皆様のご来場を心より歓迎いたします。
私たち図書館の使命は、人類の叡智を記録した資料を収集・保存し、それを未来へと手渡していくことにあります。その中でも、過去の災害に関する記録は、とりわけ重要な意味を持つと私は考えております。なぜなら、それらは単なる歴史の証言であるにとどまらず、未来の私たちが同様の危機に直面した際に生き抜くための、実践的な知恵と教訓の宝庫だからです。
本展では、私たちが守り伝えてきた災害記録という「過去からの手紙」を、皆様と共に開封したいと存じます。江戸時代の人々が書き残した克明な被害の記録や復興の道のりは、現代の防災・減災を考える上で貴重な示唆を与えてくれます。しかし、私たちが学ぶべきは、物理的な被害への対処法だけではありません。より重要なのは、彼らがその経験から何を学び、どのように精神的な回復を遂げ、文化として昇華させていったかという点にあります。
その鍵となるのが、本展のタイトルでもある「嘆きと笑い」です。災害を前にした人々の悲しみや苦しみ、すなわち「嘆き」の記録は、私たちの共感と畏敬の念を呼び起こします。一方で、不謹慎とさえ思えるほどの「笑い」や風刺に満ちた表現は、絶望的な状況下でも生きる力を失わなかった人間の強靭さの証です。この両極端な感情の表出を理解することこそ、日本人が育んできた災害文化の神髄に触れることであり、未来の災害対応に必要な文化的基盤を捉え直すことに繋がるのです。
この視点から、本展では最終章に「文化財救出と未来への記憶 ― つなぐ・守る・語り継ぐ」を据えました。これは、過去の記録を未来へ「つなぐ」図書館の役割と、災害時に文化財を「守る」現代的な課題、そしてその記憶を社会全体で「語り継ぐ」ことの重要性を示す、本展の結論とも言うべき章です。過去の経験から学び、それを未来の安全と豊かな文化創造へと活かしていく。これこそ、現代の大学に課せられた社会的責務であり、本展が目指すところであります。
この展覧会が、皆様一人ひとりにとって、過去との対話を通じて未来を考える、実り豊かな時間となることを切に願っております。結びになりますが、本展の開催にご支援ご協力を賜りました関係各位に深く感謝申し上げます。
令和7年秋
附属図書館長
西尾チヅル
このたび、附属図書館、図書館情報メディア系、そして芸術系の共催により、特別展「災害の嘆きと笑い ―日本人の記憶とこころ―」を開催できる運びとなりました。
列島に生きる私たちは、地震や洪水、噴火といった自然の猛威と幾度となく向き合ってきました。その中で、人びとは筆をとり、祈りをこめて描き、あるいは笑いや風刺へと転化することで、災いに「かたち」を与えてきました。
本展では、江戸時代の鯰絵や災害記録などを通して、そうした表現の軌跡をたどります。そこには、破壊を超えてなお残された美や、ことばにならない感情のひだが、色と線に、紙と墨に、静かに沁みこんでいるように思います。
また、災禍に失われたものの痕跡や、復興の営みを見つめ直すことは、芸術が私たちの生の奥深くに根ざしてきたことを思い出させてくれます。
本展が、過去に刻まれた美と記憶、そして人びとの「こころ」の姿を通じて、未来を照らす小さな光となることを願ってやみません。
最後に、本展の開催にあたりご協力を賜った関係各位に、お礼申し上げます。ご来場の皆様が展示を通して、日本人の災害観に触れ、多様な「こころ」のかたちを感じ取っていただければ幸いです。
令和7年秋
芸術系長
田中佐代子
このたび附属図書館および芸術系と図書館情報メディア系との共催で、特別展「災害の嘆きと笑い ―日本人の記憶とこころ―」を開催することとなりました。本系にとっては平成24年度(2012)、平成29年度(2017)に続く3回目の共催展示会です。
図書館情報メディア系は、人類の叡智と科学技術が築き上げてきた多様な情報メディアを研究対象とし、知識の蓄積や現代社会における情報流通の解明、未来に向けた情報システムの開発などに取り組んでいます。その中でも、人々の知を受け継ぐ拠点としての図書館は重要な研究対象の一つです。
日本列島は近年、度重なる自然災害に見舞われています。今後の防災・減災を考える上では、過去の災害の記録を蓄積・活用する基盤の整備が不可欠です。古文献から災害の記憶をたどる今回の特別展を通じ、多くの方々が災害情報の重要性に関心を寄せてくださることを願います。
なお、本系は平成25(2013)年に、東日本大震災の被災自治体である福島県双葉町教育委員会と震災記録の保全及び調査研究に関する協定を締結しました。今回はその成果の一部も展示しております。
令和7年秋
図書館情報メディア系⻑
森嶋厚行